|
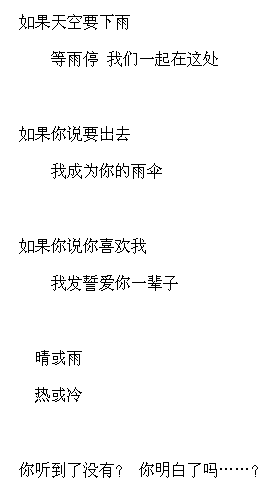
折からの雨の匂いに惹かれるように、ボクは、ふと思いついて書棚の整理をしていた。
偶然見つけた古い書き付けに、ふと懐かしさをおぼえる。
墨の濃淡も線の走りも、まったく揃わない幼い筆跡だが、よく見れば、ボクの字に似ている。
「ボクが小さい頃に書いたのかな」
詩だろうか、それとも手紙……?
韻を踏むどころか、たどたどしい口語で綴られた、明らかにこどもが書いたと思われる散文。
そのくせ、いっぱしの口説き文句のようにも取れる表現を散りばめて。
いったい誰を想って書いたんだろう
まったく憶えていないのに、なぜ、懐かしいだなんて……。
「あらまあ。九星堂の若旦那ともあろうお方が、朝から時ならぬ大掃除ですか?」
からかうような声に振り返ると、部屋の扉の前に、母が立っていた。
「おはようございます、お母さん」
「おはよう。何かおもしろいものでも見つかりまして?」
母は興味深そうに笑ったが、なぜか先刻の文章のことを告げることが憚られて、ボクはただ「いいえ。とくに何も」と、首を横に振った。
「そろそろ各支店の報告の時間ですよ。さあ、行きましょう」
にわかに老舗の女主人の顔になった母に先導されて、ボクは自室を後にした。
「佐為、行ってくるよ」
オレは、佐為の墓に花を供えて、手をあわせた。
糸のように降りしきる雨を受けて、供えたばかりの花が、ゆらゆらと揺れている。
もうちょっとしっかりした大きな花を買えたらよかったんだけど。
オレには、そのへんで野の花を摘んでくるくらいしかできなかったんだ。
「当分ここへは来られなくなっちまうけど……勘弁してくれよな。今度は、ちょっと遠いところに行くんだ」
都へ行くのは十年ぶりか。
ちっとも楽しみじゃないけど、あそこには、懐かしい思い出がいっぱいあるんだ。
佐為と一緒に碁を打って過ごした日々の思い出が。
……そうだ。
あいつも、まだ都にいるのかな。
オレの傘になってくれるって言ったヤツ。
あいつと会った日も、今日みたいに、やわらかい雨が降っていたっけ……。
如果天空要下雨 第一話
長安の都で評判の絹織物店『九星堂』。
皇帝や皇后の衣装も扱う、老舗中の老舗である。
先代の主・塔矢行洋は、囲碁をこよなく愛する穏やかな人物だった。
礼を重んじ、義に厚く、また、商いに見事な采配を振るい、九星堂の名を不動のものとした立役者でもあった。
その行洋は、十年前、持病の心臓病が悪化して天に召された。
跡を継いだのは、行洋の一人息子であるアキラだ。
アキラは、当時まだ八歳。
必然的に、母親の明子が、店を切り盛りすることになった。
そうは言っても、国中に、その名を轟かす九星堂のことだ。
大きな街には必ず支店があり、従業員の総数は、軽く千人を超える。
扱う商品の数は、天文学的な数字だ。
当然、細腕繁盛記のようにはいかない。
商いの大筋は、各支店の長にまかせ、明子はその統括を行った。
行洋の優れた経営戦略は、各支店の隅々にまで行き届いており、売り上げは良好。
行洋の他界によって、大きな打撃を受けることはなかった。
賢帝による安定した治世の影響もあるのだろう。
天下泰平な世の中、人々の生活は安定しており、一般庶民であっても、よそ行きに一枚くらいはと、絹布を買い求めることができるだけの収入を得ている。
特に、九星堂の絹といえば、誰もが憧れる有名ブランド品なのだ。
したがって、九星堂は順風満帆。
明子が新たな事柄に着手したり、特別な方針を打ち出したりする必要は、何ひとつなかった。
当時から現在に至るまで、明子から従業員に向けて、命令が出されたのは、たった一度だけ。
禁棋令である。
『九星堂においては、囲碁をたしなむことを一切禁ず』
明子は、行洋がこよなく愛した碁を禁ずるという命令を出したのだ。
行洋が可愛がっていたアキラも、幼少の頃から、自ら好んで碁を学んでいたが、母親の命令には逆らうことはできない。
アキラは、明子の言いつけを守り、棋具のすべてを自室の奥にしまい込んだ。
かくして、店や屋敷から碁盤と碁石が消え、すでに十年の歳月が経とうとしていた。
「これが各支店からの報告書、こちらが先月の決算でございます」
大きな机の上ににずらりと並んだ巻物の束を前に、アキラはため息をついた。
九星堂の朝は、こうして始まる。
豪奢な刺繍が施された布張りの椅子に腰掛け、アキラは、各部署の報告を聞き、すべての巻物に目を通す。
その斜めうしろには、母親である明子の姿。
これもまた、十年間続いている習慣だ。
実際に経営を行っているのは明子である。
だからといって、アキラがお飾りの若旦那に過ぎないかというと、実はそうではない。
稀有な経営手腕を持つ明子は、その能力を惜しみなく発揮し、それを息子であるアキラに見せて、学ばせているのである。
九星堂の主になって十年。
アキラは、明子から学んだことをもとに、少しずつ、店の経営に参加し始めていた。
すべての報告が済み、アキラが席を立とうとしたところで、執事が前に進み出た。
「今日から、お屋敷にお仕えいたします新しい下働きの娘が参っております」
下働き。
明子は、その言葉を聞いて、興味なさそうに手を振った。
「そのようなこと、女中頭にでも申しつけておきなさい」
明子は、先々帝の皇女だった。
降嫁したとはいえ、気位の高い明子にとっては、使用人の動向など、取るに足らぬ些細なことなのだ。
明子は長衣の裾をさばき、部屋を出ていった。
「ボクは、今日一日、部屋で書棚の整理をしています。何かあったら呼んでください。下働きの娘さんのことは、女中頭の市河さんに頼めば、世話をしてくれるでしょう」
アキラは、執事にそう言い置いて、自室へと向かったのだった。
その頃、屋敷の裏にある小さな建物の一室に、粗末な身なりの少女が立っていた。
少女の名は、ヒカル。
八歳の時に養父と死に別れ、天涯孤独の身の上となって以来、いろいろな屋敷で下働きをして暮らしている。
ヒカルは、きょろきょろと部屋のなかを見回した。
「さすが天下の九星堂だよなあ。使用人の休憩室にまで、カネかけてやがるぜ」
さほど凝った造りではないものの、窓の格子には飾り文様が掘り込まれている。
しっかりと磨かれた木の床は、まるで鏡のようにつややかで、塵ひとつ落ちていない。
机のうえの古い燭台は、主人たちが以前使っていたものだろうかと、ヒカルが観察していると、背後の扉がひらく音がした。
「待たせちゃったかしら。ごめんなさい。あなたが進藤ヒカルさんね」
愛想よく声をかけながら室内に入ってきたのは、若い女性だ。
自分の名前を知っているということは、ここの使用人を取りまとめる役職の女中だろうと、ヒカルは、ぺこりと頭をさげた。
「はい、ヒカルです。初めまして」
「わたしは女中頭の市河よ。よろしくね」
市河の年齢は、二十代半ばといったところだろうか。
この若さで九星堂の女中頭を務めるとは、きっと才覚のある女性なのだろうと、ヒカルは想像した。
「まずは制服に着替えてね。大きさは……一番小さいので十分みたいね」
市河に手渡された制服を、ヒカルは、衝立の裏でひろげてみた。
(さすが九星堂。使用人の制服の布も、いいもん使ってるな)
藤色の短衣に、若草色の褲子。
襟と袖の折返しには、紺色の刺繍が施されている。
下働きの娘のためのお仕着せ服にしては、ずいぶんと豪華だ。
女中頭である市河の制服にいたっては、上等な絹が使われている。
一般市民の晴れ着並みの値段はするだろう。
ヒカルが着替えて出てくると、市河は、屋敷のしきたりについて説明を始めた。
「あなたは、いろいろなお屋敷で働いていたのだから、たいていのことはわかってるわよね。ここも、よそのお屋敷と変わらないんだけど、ひとつだけ注意してほしいことがあるの」
市河は、十年の使用人歴を持つヒカルに、使用人の心得について語る必要はないだろうと、ほとんどの説明を省略し、九星堂独特のルールだけを話すことにした。
「このお屋敷には、禁棋令が布かれているの」
「キンキレイ?」
ヒカルは、意味がわからずに聞き返した。
「九星堂の関係者は、囲碁に関わってはいけない。それだけの話よ」
「なんで碁を打っちゃいけないんだ?…っととと、いけないんですか?」
「使用人……もっぱら年を取ったおじいさんたちが、碁にかまけて仕事をさぼるのを防ぐためじゃないかしら。現在の九星堂の女主人でいらっしゃる明子さまがお決めになったことだけど、詳しいことは知らないわ」
碁にまったく興味がないのだろう。
市河は、なんでもないことのように言った。
だが、ヒカルは、さっと顔色を変えた。
(マジかよ……。禁棋令なんて、そんなの聞いてないぞ)
ぽかんと口をあけて、大きな瞳を泳がせる。
「碁なんて、おじいさんたちの遊びでしょう? わたしたちには関係ない話よ」
カラカラと笑う市河に隠れて、ヒカルは肩を落とした。
「それじゃあ行きましょう。お屋敷の中を案内するわ」
先導して歩く市河のうしろについていきながら、ヒカルは、首からさげた護符袋をぎゅっと握りしめた。
「……関係ない…か……」
粗い布地を通して、まるくてひらべったい感触をてのひらに感じながら、ヒカルは小さくつぶやいたのだった。
|