|
自分が捨て子であることなど、ヒカルは、まったく構いはしなかった。
ただ、佐為を悪く言われたことだけは、我慢できなかったのだ。
それでも、アキラと向かい合って話しているうちに、明子の侍女たちへの怒りは収まり、いつしか、佐為への想いだけが、ヒカルの胸中を占めていた。
語り終えたヒカルの顔には、追懐と憐惜の色が浮かんでいた。
だが、痛ましく歪められた柳眉が、それだけではないことを示している。
アキラは何も言わず、ただ、ヒカルが話し始めるのを待った。
「佐為は……オレが、近所のヤツらに、これを見せびらかしに行ってるあいだに……逝っちまった」
長い沈黙のあと、ヒカルは、護符袋を撫でながらつぶやいた。
「この護符袋をもらった次の日だったよ。その日は雨が降ってて、誰も外で遊んでなんかいなかった。それでもオレは嬉しくって、早く誰かに見せたくて、都中を走り回ってたんだ。佐為をひとりぼっちにして……」
ヒカルの目から、ぽたりと大粒の涙がこぼれた。
「顔見知りのヤツは誰もいなかったけど……お寺の門のところで、同い年ぐらいのこどもが、雨宿りしてるのを見つけた。オレが、そいつに護符袋を見せて、得意になってはしゃいでるあいだに、佐為は……佐為は……」
自分の欲求を優先し、佐為の最期を看取れなかったことへの後悔と、病床の彼を困らせ、無理を強いたことへの慙愧。
悔やんでも悔やみきれないと、ヒカルは嗚咽をもらした。
涙は滂沱のごとく、とめどなくあふれ続ける。
しゃくりあげる小さな肩がいじらしくて、アキラはそっと視線をそらし、手巾を差し出そうと懐を探った。
だが、そのとき、ヒカルの手のなかの護符袋が目にとまり、ふと考え込んだ。
「……蘭若寺か?」
アキラは、ぽつりと言葉をもらした。
「キミがそのこどもに会ったのは、都のはずれにある蘭若寺か?」
都で寺といえば、蘭若寺を表す。
高い塔と大きな山門のある名刹だ。
ヒカルの言う寺がどこなのかを想像するなら、アキラでなくとも、百人が百人、真っ先に蘭若寺の名を挙げるだろう。
しかし、今、寺の名前を特定する必要があるだろうか。
ヒカルが、ごしごしと目をこするのを見ながら、アキラは、ひとつ咳払いをした。
「……雨がやむまで、ここで一緒に雨宿りしよう」
詩を朗詠するかのような、少し節をつけた言い回しに、ヒカルは、不思議そうに顔をあげた。
いや、正しくは、言い回しではなく、その言葉の内容に、思うところがあったようだ。
涙に濡れたまつげを震わせて、じっとアキラを見つめる。
そんなヒカルの表情に、アキラは、何かを確信したようだ。
「どうしても行かなければならないと言うなら、ボクが……」
アキラが問いかけるように言葉を切るのを受けて、ヒカルは続けて言った。
「…………傘になってあげるよ?」
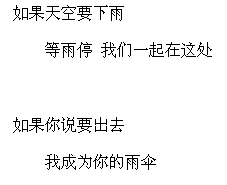
「もしかして、あのときのこどもって……」
「うん、ボクだよ。……キミの話を聞くまで、ずっと忘れていたけど、はっきりと思い出したよ」
アキラは、少しバツが悪そうな顔をして頷いた。
「父が病に臥せっていた頃、蘭若寺のお坊さんに、よく祈祷してもらっていたんだ。父が亡くなったあとも、父の冥福を祈って、母は、時間に折り合いをつけては、熱心に通っていたよ」
アキラは、幼い頃の記憶を辿るように、そっと目を伏せた。
行洋が亡くなってまもなくの頃。
亡き夫の供養のためにと、明子が、蘭若寺の高僧に祈祷を依頼したことがあった。
その日は朝から雨模様だったが、せっかく店の仕事の都合をつけたのだからと、明子は予定を変えずに、アキラを伴って蘭若寺を訪ねたのだ。
アキラの健やかな成長の祈願も兼ねていたのだが、まだ幼いアキラには、そのありがたみは理解し難かった。
祈祷が始まってすぐに退屈してしまい、アキラは、こっそりと部屋を抜け出した。
大店の一人息子であるアキラは、もともと、同年代の友達と過ごすことが少ない。
ひとりで遊ぶことには慣れている。
小雨のなかを縫って、山門のあたりまで探検気分で歩いてきたところで、急に雨脚が強まった。
山門の大きな屋根の下で雨宿りをしていると、同じ年くらいのこどもが走ってきた。
ずいぶんと元気のよい走りっぷりだが、胸元に結んだ桃色の絲帯から察するに、女の子だろう。
雨よけのつもりか、古びた手巾を頭にかぶっているが、もうすっかりずぶ濡れだ。
アキラのそばに駆け寄って、人懐こい笑顔を向けてきた。
「なあなあ、みてくれよ、これ!」
その女の子は、濡れた手巾もそのままに、首からさげた小さな袋を差し出した。
「…………」
上等な絹織物に囲まれて暮らしているアキラには、粗末な布袋にしか見えなかったが、持ち主の瞳が、あまりにも嬉しそうに煌いていたので、正直な感想を述べられなかったのだ。
アキラが答えないのを不快には思わなかったようで、彼女は、にっこりと目を細め、得意気に胸を張る。
「さいがつくってくれたんだ。オレのなんだぜ、これ。いいだろー♪」
誰もが持っている護符袋を、なぜこんなにも自慢して見せびらかすのか。
アキラは不思議に思ったが、調子をあわせておくことにした。
不用意な発言をして、その無邪気な瞳を曇らせてしまいたくなかったのかもしれない。
「へえ、護符袋か。あたたかみのある素朴な織りが素敵だね」
「だろ? だろ? えへへへ」
嬉しそうにくるくると踊り出す姿を見て、アキラは、自分の選択は正しかったと安堵した。
雨のなか、いきなり走り寄ってきた女の子。
お世辞にも身なりがよいとは言えない、どこの誰とも知れない、行きずりのこども。
いつもなら、しつけの行き届いているアキラが、見知らぬ者と親しく言葉を交わすことなどありえないはずなのに。
雨宿りの退屈まぎれだろうか。
それとも、この子の瞳の輝きに惹かれたのだろうか。
アキラは、いつまでも一緒にいたいと思った。
だが、護符袋を見せて満足したのか、彼女は帰ると言い出した。
同年代の友達を持たないアキラは、どうやって彼女を引きとめればいいのかわからない。
そこで、作り方をおぼえたばかりの詩を、即興で詠じた。
もしも このまま雨が降り続くとしたら
ボクと一緒に ここで雨宿りしてくれる?
「だめだよ。さいがまってるんだから」
「そ、そうか……。残念だな」
だからといって、そう簡単には、あきらめられない。
どうしても行くのかい?
それなら ボクが傘になってあげるよ
「にんげんが、どうやってかさになるんだよ。ヘンなやつ」
「へ、ヘンって……。これは、詩の常套文句じゃないか」
せいいっぱい背のびした台詞も、澄んだ瞳で首を傾げられては台無しだ。
それなら、もっとわかりやすい言葉を……と、アキラが思いあぐねていると。
「あっ。雨があがりそうだ。じゃあな!」
一瞬遅れて振り返ったアキラの目に映ったのは、山門の階段を駆けおりていく後ろ姿。
アキラは、がっくりと肩を落とし、しだいに小さくなっていく人影を、いつまでも見送っていた。
遠い昔を一通り思い出して、アキラが現実の世界に戻ってくると、ヒカルは焦点のあわない目をして座り込んでいた。
「……? 進藤?」
名前を呼ばれれば、ちらりとアキラの顔に目を向けるが、すぐに視線を泳がせてしまう。
(進藤は、ボクを憎むだろうか)
決してアキラのせいではないし、恨まれるのも憎まれるのも、筋違いである。
だが、アキラは、自分が非難されることで、ヒカルの気持ちが軽くなるのなら、それでいいと思った。
(だけど……進藤はきっと、ボクを憎んで罪の意識から逃げるようなことを、潔しとはしないだろう)
アキラは、ヒカルの視線をとらえるべく、居住まいを正した。
「ボクは、あの日、キミに出会えて嬉しかったよ」
「え?」
「今の今まで忘れていたのに、こんなことを言うのは、我ながら調子がいいとは思うけど」
アキラは、ヒカルの目を見つめて、真摯に訴えた。
「あの日、キミとボクが出会ったのは、藤原佐為先生のお導きなんじゃないかな」
「…………佐為の?」
驚いた声で返すヒカルに、アキラは大きく頷いた。
「藤原先生の遺志を継いで、碁の道を歩むキミの相手として。互いに切磋琢磨していける同志として。ボクを選んでくれたんじゃないかな」
佐為・遺志・碁。
それらのキーワードが、ヒカルの琴線に触れたようだ。
ヒカルは瞬きもせずに、アキラを見つめている。
「キミが蘭若寺へ行ったのは必然だったんだ。藤原先生は、ボクたちを会わせたかったに違いない」
「…………」
「初めて会った日から今日まで、ずいぶんと長い年月が流れた。なぜ、あの日でなくてはならなかったのかはわからない。だけど、この十年は、きっと必要な時間だったんだと思う」
そう言いながらも、アキラには確信はなかった。
すっかり失念していただけの空白の十年を「必要な時間だった」だなんて、こじつけもいいところだという自覚もあった。
それでも、蘇張の弁とばかりに言葉が自然と連なっていくのは、アキラ自身、どこか信じるところがあったのかもしれない。
悔恨の念に囚われて泣き続けるよりも。
他人を憎んで自らの苦しみから逃れるよりも。
然るべくして起こったことだと、受け入れてほしかった。
過去を嘆いて瞳を曇らせるのでなく。
怨嗟や憎悪に眉をゆがめるのではなく。
晴れやかな笑顔を見せてほしかった。
「そんな話……信じらんないよ……。そんなの、ただの偶然じゃんか」
ヒカルは、まだ少し濡れたままの睫毛を伏せた。
「偶然? キミは、どれだけの人間が都に住んでいると思っているんだ?」
何十万という人間のなかで、あの日、蘭若寺の山門にいたのは、たったふたり。
しかも、ふたりとも囲碁が好きで。
十年後に再会を果たすなんて。
「単なる偶然で済ませられることだろうか。人間には見えない、何か大きな力がはたらいているとしか思えないよ」
見えない力に導かれて、ふたりは出会った……。
運命の赤い糸の伝説とも言い換えられる言葉に、言ったアキラも、言われたヒカルも、顔を赤らめてうつむいた。
ちょうどそのとき。
「「ただいまー」」
扉の外から声がかかった。
あかりと明日美が、仕事を終えて戻ってきたようだ。
「あら? 若旦那さまじゃありませんか」
「侍女の部屋で、何をしていらっしゃるのですか?」
言葉の端々に棘がある。
あかりも明日美も、金子の作戦通り、アキラを悪者だと思い込んでいるのだ。
「ぼ、ボクは、これで失礼するよっ」
あわてて部屋を飛び出していくアキラの頬は、まだ染まったままだ。
座り込んでいるヒカルも、また同様だ。
「なになになに? もしかして……わたしたち、お邪魔だった?」
「ひ~か~る~? どういうことよー。お姉さんたちに白状しなさーい」
あかりと明日美は、じりじりと膝を進める。
餃子論争から始まったヒカルの長い午後は、まだまだ終わりそうになかった。
|