|
如果天空要下雨 第十五話
「進藤を……お母さんの侍女に……?」
思いもよらない話に、アキラは、明子の顔を凝視した。
(なぜ、お母さんは、進藤に興味を持ったんだ? もしや、ボクたちが碁を打っていることを、どこかで聞いたのか……?)
アキラの額に、いやな汗が流れる。
「元気いっぱいで、とてもかわいい子ね。ああいう子が側仕えをしてくれたら、一緒にお茶を飲んだり、おしゃべりをしたり。きっと楽しいと思うのよ」
アキラの不安をよそに、明子はただ、ヒカルを高く評価しているだけのようだ。
ヒカルと過ごすお茶の時間を空想しているのか、楽しそうに微笑んでいる。
(お母さんと進藤のあいだに、どんな接点が? いや、それどころじゃない!)
禁棋令を破っていることとは無関係だということはわかったが、ほっとしている場合ではなかった。
このままでは、ヒカルと碁を打つ機会を失ってしまう。
アキラは、眼光鋭く明子を見つめた。
「お断りします」
きっぱりと言い放ったアキラを見つめ返し、明子は「まあ」と、小さく声をあげた。
その「まあ」には、生まれてから18年間、一度も母親に逆らったことのないヘタレ息子、もとい、孝行息子が…という心情が、ありありと表れている。
「アキラさんがそんなにムキになるなんて。それほどまでに優れた侍女なのね。ますます欲しくなってしまうわ」
「ダメです!」
アキラは、瞬きひとつせずに、明子の目を見つめている。
いや、睨みつけていると言ったほうがいいかもしれない。
明子は怯えたように目をそらし、折衷案を提示した。
「そ、そう。……それなら、時々、午後のお茶に呼ぶくらい」
「ダメだと言ったらダメです! 絶対にお断りします!」
アキラは、明子の言葉を遮り、断固拒否の構えを見せた。
「お話がそれだけでしたら、これで失礼します」
くるりときびすを返して、立ち去っていくアキラの背中を見送って、明子は「はあ…」と、ため息をついた。
「せっかく、いい子を見つけたのに」
花園で、ヒカルの言葉を聞いて、明子は興味を持った。
自分に仕える侍女たちは、おべっかばかりで実がないと、常々不満に思っているところでもあった。
九星堂の女主人に仕えているのであって、明子に仕えているのではない……そんな気配を何度となく感じていたのだ。
『奥様はきっと……今でも旦那さまのことが、すごく好きなんだよ』
偶然、花園の前を通りかかったときに、その言葉が聞こえてきただけで、どんな話をしていたかまではわからなかった。
だが、明子には、それで十分だった。
明子が今でも行洋を愛しているのは、まぎれもない事実なのだから。
「それにしても」
明子は、アキラの館の方向を振り返り、うふふっと笑った。
「あのアキラさんが、あんなに反対するなんて。女の子に興味を持つ年頃なのね」
ヒカルを自分の侍女にすることはできなかったが、なんとなく嬉しそうな明子であった。
一方、アキラは。
石張りの床を踏み割るような勢いで、回廊を渡っていた。
「どうしていきなり、進藤を……」
先刻の明子の言葉を思い出して、アキラは、外塀に切り取られた空を睨みつけた。
晴天の霹靂とはよく言ったもの。
アキラの胸中を表す比喩に留まらず、実際に、いつのまにか空模様が怪しくなっていた。
さわやかな朝の陽射しから一転して、鈍色の雲が低く立ち込めている。
ほどなくして、雨が降り始めることだろう。
アキラは自室に着くと、荒々しく扉を閉め、気持ちを落ち着けようと、お茶を淹れた。
茶器を持って碁盤の前に座り、ゆっくりと深呼吸する。
湯飲みに口をつけても、イライラした気分は、おさまらなかった。
「進藤の淹れてくれる、秘密のお茶が飲みたい……」
腰をおろして、まだほんの数分だというのに、アキラは立ちあがった。
うろうろと部屋のなかを歩きまわり、時々立ちどまっては、ふう…っとため息をもらす。
「まったく……。お母さんには驚かされる。せっかくめぐりあえた同志なのに」
今の落ち着かない気分の原因について、アキラは、大切な同志を失いかけたせいだろうと分析した。
だが。
その危機は回避できたはずなのに、今すぐにでも、ヒカルに会いたいと思うのは、いったいどういうことだろう。
水汲みが終われば、手押し車を押して、「お茶をお持ちいたしましま~」と、ふざけた口調で、秘密のお茶を運んできてくれると、頭のなかではわかっているのに。
いくら考えても、しっくりくる答えは浮かばない。
覇気のないヘタレた熊のように、もそもそと部屋中を徘徊しながら、ため息をつくばかりだ。
そのうちに、隅に置かれた書棚が目にとまった。
蜂蜜の入った壷に引き寄せられる西洋の熊よろしく、アキラはふらふらと書棚へと向かい、奥のほうにしまい込んだ棋譜の束を取り出そうとした。
古人の優れた棋譜でも見れば、少しは冷静になれるかと思ったのだ。
半分見栄で並べてある四書五経を脇に寄せ、棚の奥へと手をのばしたそのとき。
はらり
古びた書きつけが、舞い落ちた。
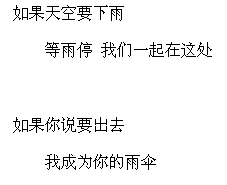
幼い文字に、たどたどしい文体。
韻も踏まず、頭の「もしも」だけが共通点だ。
「これは……詩なんかじゃないな」
アキラは、くすりと笑った。
出来損ないの文章だと馬鹿にしたわけではない。
続きの部分を見て言ったのだ。
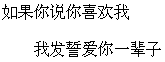
「もしもキミがボクのことを好きだと言ってくれたら、ボクはキミを一生大切にすると誓うよ……か。生意気だな。たった8歳のくせに、ラブレターなんか書いて」
初めて書いたラブレター。
相手は、ほんの少しのあいだ一緒に雨宿りしただけの女の子。
宛先のない手紙は、十年間、アキラの部屋の書棚の奥に忘れられたまま、決して届けられることはなかった。
「いや……今ならもう届くんだ。ボクは、彼女の住所も名前も知ってる」
アキラは、文机に向かって墨をすった。
筆にたっぷりと墨を取り、書きつけの文字を、真新しい線で塗りつぶす。
「もしもキミが好きだと言ってくれたら……この部分は、いらない。キミを一生大切にしたい。ただそれだけなんだ」
口に出して、初めてすっきりした気分になった。
アキラは筆を置き、窓辺に寄った。
窓を少し開けて覗けば、晴れ晴れとした気持ちとは裏腹に、空からは大粒の雨が降り始めていた。
「今日は、たくさん打てるぞ……か」
それは、雨の日のヒカルの口癖だ。
ヒカルが水汲みに行く回数が少ない日は、当然、対局する時間が増える。
ヒカルが嬉しそうに笑うものだから、アキラも、雨の日を楽しみにするようになっていた。
だが、今。
「……ボクは、なんて馬鹿だったんだ」
窓外の景色を見つめるアキラの表情は、悔しげに歪められていた。
低い空から絶え間なく落ちる雨粒。
回廊にまで吹き込む激しい風。
泥の色をした水たまり。
この酷い天候のなか、ヒカルは、水汲みをしているのだ。
「進藤はただの同志じゃない。ただの侍女なんかじゃない。進藤は……進藤は、ボクの大切なひとだ」
アキラは、雨空に向かって、自覚したばかりの思いを吐き出した。
「いや~、すんげえ雨だな~。おかげで、今日は、たくさん打てるぜ」
カラカラと豪快に笑いながら、ヒカルが部屋に入ってきた。
水汲み用の制服から、侍女の制服に着替えたばかりなのか、後ろ手にエプロンを結びながら。
適当に拭いただけと思われる濡れたままの髪の先からは、ぽたぽたと雫が落ちている。
そんなヒカルの状態を見るや否や、アキラは手巾をつかんで駆け寄った。
「進藤! ちゃんと髪を拭かなきゃダメじゃないか!」
ヒカルの頭に手巾を乗せて、ガシガシと水気をぬぐう。
「いいよ、そんなの。ほっときゃ乾くって。それより、早く打とうぜ。雨が降ってくれたおかげで、たくさん打てるんだから」
「たくさん打てなくてもいい。キミが雨に濡れて、寒い思いをするくらいなら。キミが風邪をひいてしまうくらいなら。雨なんか……雨なんか降らなければいいんだ!」
ヒカルの頭に乗せた手巾に手をかけたまま、アキラは叫んだ。
興奮状態の怒声を、至近距離で聞かされたヒカルは、たまったものじゃない。
きーんと耳鳴りがした。
いや、それどころではない。
(なんだなんだ? なんか今、すんごいことを言われたような気がするんだけど)
ヒカルの身を案じてくれる言葉ではあったが、それだけではない何かを含んではいなかったか。
ヒカルは、なんとなく恥ずかしいような気持ちになって、言葉を探した。
「えーっと、その、なんだ。こうしてると、初めてこの部屋に来たとき、塔矢が髪を拭いてくれたのを思い出すよな」
取り繕うような笑みを浮かべ、上目遣いでアキラの様子を探ると、アキラは、大真面目な表情で、ヒカルを見つめていた。
「ボクは、こうしてると……初めてキミに会った日のことを思い出すよ」
アキラは、手巾を頭巾に見立てて、ヒカルの頭にすっぽりとかぶせた。
金色の前髪を隠してしまえば、そこには、確かにあの日の少女の面影があった。
「あの日、この金色を見ていれば、ボクは絶対に忘れたりしなかったのに。雨さえ降っていなければ、この輝くような黄金の前髪を、はっきりと見ることができたのに」
手巾のあいだから、金色の髪束をひとすじ、愛しむようにすくい、「雨宿りが、ボクたちを会わせてくれたのに、本末転倒もいいところだね」と、アキラは笑った。
少し口をとがらせた中途半端なその笑顔が、あまりにも可愛らしくて、ヒカルは、思わず目をそらせた。
「なんだよ。ヘンなヤツだな。何が言いたいんだよ。はっきり言えっての」
照れ隠しとばかりに悪態をついたが、それは、天然のおねだり言葉に他ならなかった。
ヒカルに先を促されるようにして、アキラは思いを告げた。
「ボクはね。……初めて会ったときから、キミのことが好きだったんだよ」
その言葉を聞かされては、ヒカルはもう、悪態をつくどころではなかった。
耳まで真っ赤になっているヒカルの手をとって、アキラはさらに続ける。
「キミがボクのことをどう思っていても、キミを大切にしたいという思いに変わりはない。だけど、正直なところ、キミの気持ちが知りたいというのも事実だ」
恥ずかしそうにうつむくその態度で、まるわかりだというのに。
アキラには、そんなヒカルの様子に気がつくほどの余裕はなかった。
「と、とりあえず、ボクがニギるよ。…………あとで、返事を聞かせてもらえたら嬉しい」
もう、いっぱいいっぱいだったのだろう。
アキラは、さっさと碁に逃げたのだった。
(まああああぁぁ。やるじゃないの、アキラさんったら♪)
部屋の外で、出歯亀よろしく聞き耳を立てていたのは、他でもない明子だった。
防音工事が施されてはいても、窓が開いていては、なんの意味もない。
(あんなふうに反対したくらいだものね。思ったとおりだわ。アキラさんは、あの侍女のことが好きだったのね)
主と侍女のキケンな情事。
そんな腐れた言葉が頭に浮かんだが、明子は、それをすぐに振り払った。
(あの朴念仁のアキラさんが恋に落ちたのよ。しかも、わたくしが侍女にしたいと思うほどの娘と。うふふ、大歓迎だわ)
窓の下にかがみ込んで、明子は、くふくふと忍び笑いをもらしている。
先々帝の皇女の名が泣くというものだ。
(それにしても、アキラさんったら、意外に口説き上手じゃない。もしかしたら、すぐにでも押し倒しちゃったりなんかして……)
明子は窓に手をかけ、ゆっくりと腰をのばした。
わずかに開けられた窓の隙間から、そーっと部屋のなかを覗き込む。
だが、誰もいない。
(あらまあ。本当に、その場に押し倒しちゃったのかしら)
もっと下のほうまで見えるようにと、さらに覗き込めば、床に近い位置に若いふたりが見えた。
抱き合うでもなく。
横たわるでもなく。
向かいあって座るふたりのあいだには……碁盤が置かれていた。
|